 一般社団法人 熊本青年会議所
一般社団法人 熊本青年会議所
2025年度 第71代理事長 中田 慎二
はじめに
「ラグビーは、いちはやく少年を大人にし、大人に永遠に少年の心を抱かせる。ラグビーから学んだ事は、人を制圧する事ではなく、人と共に生きていく事だ。だからラグビーは、素晴らしい。」という言葉を残した、元ラグビーフランス代表主将ジャン・ピエール・リーブスに憧れた父の影響で幼少期よりラグビーを始めました。
ラグビーは、集団スポーツの中でも最大人数の集団競技であり、体が大きな人もいれば、身軽な人もいる、背の高い人がいれば、低い人もいるというように様々な特徴をもった人が、それぞれの見合ったポジションで役割を果たすものです。また、自分1人の力では,チームを勝利に導くことができず、いつ、どんな場面でも仲間の力が必要であり個を尊重しつつも組織を重んじて行動します。そして、体と体がぶつかり肉体的にも精神的にもきつい激しい競技ということもあってか、同じ経験や時間を共有した大切な仲間との結束は、非常に固いものとなります。この仲間との関係は、チームに所属している間だけではなく、卒業後も引退後も続いて、さらに結束力が固くなり生涯の友となる人も少なくないのです。
そして、選手だけでなく、指導者やスタッフといった関係者とも強い絆で結ばれます。
プロ選手を引退するまで私の青春は、ラグビーに没頭し、殆ど全てをつぎ込みました。 引退後、熊本に帰郷し父が営む家業に就いた後、父も叔父も青年会議所のOBであったこともあり熊本青年会議所の門を叩きました。
入会翌年に平成28年熊本地震が発災しました。その当時のリーダーは、被災直後より「熊本青年会議所がこの状況で動かないなら存在する意味はない」という気概を行動で示してくれました。熊本に住み暮らす人々の為に即決断し、行動していく中で、自分が心から信じる価値観や考え方を、困難な状況に直面しても曲げず貫いていく。私はこのような「人」に感化されて活動してきました。
私にとって青年会議所の活動は、よく言われる「大人の部活」、その言葉で表せます。学校で行なってきた部活とは目的も違います。しかし、目的やビジョンに向けて活動する過程や、その過程の中にある修練によって友情が生まれ仲間ができる環境、その仲間との思い出が作られる場所は、まさに大人の部活と言えるのではないでしょうか。青年会議所とは、明確な理念の基、掲げられたビジョン、ミッションに向けて40歳まで活動していく、活動できる部活であると、私自身の経験から感じています。私は、熊本の「明るい豊かな社会の実現」に向けて、青年が何をすべきかを真剣に考え、高い熱量で議論し、共有を図り、物凄いスピードで行動に移していく先輩方の姿を間近で見てきました。本能で活動する先輩方を間近で感じ、私自身もそんな人でありたいと強い気持ちで共に活動してきました。熊本を皆で豊かにしていきたい、これからの時代と共に変化できる組織として、今より成⾧し、青年らしい理想を掲げて、能動的に活動していきます。
70周年から未来へ向けて
1953年6月26日に発災した白川大水害。県内全域での死者は339名を数え、熊本市にも甚大な被害を与えました。この時、有志で集った青年達が復興に向け活動し、そのメンバーを中心に1955年4月26日に43名の青年達により熊本青年会議所が創られました。我が国、そして熊本のまちは、経済的・文化的発展、社会インフラの整備・拡充等を次々と現実のものとし、数々の国難と地域の危機を乗り越えながらも世界をリードする経済大国として一角の地位を確立してきました。この歴史の、どの時代にも必ず国やまちを想う青年の弛まぬ努力と行動があったはずです。ここ10年の熊本青年会議所の運動・活動を振り返ってみても、熊本地震からの復興へ向けた活動、国際アカデミーの開催、九州コンファレンスの開催など熊本のまちづくりに対して寄与してきました。
熊本青年会議所の過去の歴史を遡れば明らかな通り、目まぐるしく変わる社会情勢の中で、その時々の課題に正対し果敢に挑み、最適解を模索しながら熊本の「明るい豊かな社会の実現」に向けて、先輩達は数限りない輝かしい功績を残されてきました。この幕開けからこれまでの歴史と志を受け継ぐ中、本年、熊本青年会議所は創立70周年という節目を迎えます。歴史を振り返り先人の想いを継承し、感謝の気持ちを伝える周年式典と、これからを見据えた節目の年に相応しい新たな事業を実施いたします。さらに、80周年、90周年、100周年と続いていく組織として、これまでの成果を再確認するとともに、行政とも連携した青年らしい夢溢れる未来への中期ビジョンを策定し発信していきます。
70周年事業の成功は組織全体のモチベーションやブランドイメージの向上にも繋がり、組織の結束力を高めます。そして、次の世代への新たな一歩を踏み出すための熱いエネルギーが生まれ、熊本の国際都市化へ向けた原動力となります。
子ども達へ
これからの人材教育において文部科学省は現在、変化の激しい社会に対応して、探求的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習をおこなっています。その一つとして、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく為の資質・能力を育成することを目標とする総合的な学習(探求の時間)をスタートさせています。一方、国内のグローバル化は社会に多様性をもたらし、情報化や技術の進展により社会には質的変化がもたらされました。このような時代においては、従来の知識伝達型教育システムから脱却し、多様性を包摂する環境の中で自ら課題を設定する能力を培う課題創造型人財の育成が必要であり、単一の専門知識だけでなく、異なる分野を結びつけ、新たなアイデアやイノベーションを生み出す力のある人財が求められています。
私は、創立50周年記念事業から12回続いた阿蘇熊本徒歩の旅事業の委員⾧を経験させていただきました。メンバーや先輩方からのご協力・叱咤激励もあり無事に担いを務めることができました。肉体的にも精神的にも大変な中、1つの目的に対して、メンバー一人ひとりが委員会の垣根を越えて能動的に行動し、4泊5日の時間を共有しました。だからこそ、その時共に活動した大切な仲間との強い絆は、今も続いています。この経験は、青年会議所ならではの特別な経験であり、達成感から生まれる高揚感は、一生忘れることのできないものです。このような「生きる力を育む事業」を構築し継続された先輩たちに敬意を表すとともに、70周年記念事業として、熊本青年会議所という1つの組織がさらに結束を深め情熱を持って果敢に挑戦していきます。
その想いを大切にしながら、仁徳国際青年商会と丹絨武雅国際青年商會の国際的な姉妹JCと連携して、子ども達が異文化に触れる機会を創出します。異文化に触れ、他者を理解しようとする姿勢を持つことで相手を尊重する意識が生れ、自分の価値観に気付く事となり郷土愛の醸成へと繋がります。70周年記念事業として「これからの生きる力を育む」をテーマとして国際青少年事業を構築します。
また、熊本青年会議所が⾧きに渡り続けている熊本県立盲学校生徒招待アイススケート事業は、本年で58回目を迎えます。スケートリンクに下りて、時々転びながらも何度も立ち上がり楽しそうに滑る姿。「一緒に滑れてとても楽しかったです。ありがとうございます。」「来年も楽しみにしています。」といった一緒に滑った子ども達から届く手紙にある言葉が事業継続の力となり、半世紀以上続く事業となっているのだと思います。また、子ども達の楽しそうな中にも挑戦する姿に我々メンバーも多くの元気をもらう事業でもあります。一人でも多くのメンバーに、これからも続くこの素晴らしい事業を体感してほしいと思います。豊かな心で子ども達と接することにより共生社会の実現への一助となることを願い、本年も継続して参ります。
ブランディング
20世紀における広告や情報発信は、「4マス」と呼ばれるテレビ、ラジオ、雑誌、新聞が中心でしたが、近年多くの人たちがこうしたメディアとの接触時間が減り、インターネットを利用する時間が増えています。熊本の明るい豊かな社会の実現に向けた一つ一つの活動をより広く、より効果的に知ってもらうためには、SNSの活用が不可欠です。しかし、容易なSNSでの発信による炎上騒ぎにみられるように、組織や企業が常識や道徳から反した行為が発信された際に、ブランドイメージが失墜するような事態が多く発生しています。また、「善行すれば評価される」と信じられてきましたが、情報量が多い現在では、埋もれてしまい市民に届きづらい状況となっています。これからは、組織の価値に加え、組織としてどうあるべきなのかという「態度」を徹底的に考え、掲げたビジョンを実践していくことを発信して認知されることが重要となります。さらに、実行力の伴った運動の実現には、認知度の向上と、運動に対する幅広い共感、さらには熊本青年会議所を好きになってもらうことが必要です。
まずは、熊本青年会議所を知ってもらう発信をこれまで通り継続的に続け、イメージの定着化に繋げます。そして、重要となるのがHPの更新やSNSの更新です。毎年、素晴らしい事業をおこなっていますが、単年度単位で広報活動をしている現状があります。本年度は、中⾧期で広報とブランディングの仕組み作りを考え、実践していくことにより多くの熊本青年会議所のファン獲得へと繋げます。
熊本青年会議所を好きになってもらう上で、大事にしたい視点があります。それは、人間は倫理と感情の二つの自分をもっており、ブランディングは、この情緒的な「好き」という感情を揺さぶることがとても重要であり、効果的であるという点です。感情に訴え「好き」になってもらい、熊本青年会議所のファンとなることで運動の効果を最大限化します。さらには、様々な知恵をもって計画し、様々な人たちと協働することで私たちの組織や運動が市民の皆様に「好き」と感じてもらえる最短ルートをとる必要があります。叡智を集結させ、青年会議所運動を最大化することでブランド力を強化していきます。
求められる「体験・経験」探し
熊本の人口は、2050年には70万人を大きく割り込み、約65万人になると予想されています。熊本に限らず、生産人口の減少、若者の都市部への流出といった地方都市に共通の課題は、常に地域の持続可能性を語るとき重大な課題として取り上げられ、その解決策についても様々に議論されています。全国の多くの自治体では、このような諸問題を解決する制度を独自に策定していますが、その施策の数々は統計的データや定量的な指標に基づいたまちの総合政策の一環としての手法に留まるケースもあり、必ずしも未来を生きる世代の視点や意思、現場の声が正確に反映されているとは限りません。まちのビジョンを定め未来をつくる枠組みを生み出すのは私たち青年の使命ですが、一方で我々が現状において想像し思い描く未来を生きるのは、まさに今の子ども世代であり、彼ら、彼女らがどのように生き、どのように社会と関わり、この地域で持続的に住み暮らしてゆくのか、その具体的な形を導くのものまた重要な役割です。
永きに渡り郷土を想い、地域に寄り添いながらまちの未来をつくる運動を展開してきた熊本青年会議所こそ、次の世代のために何を託せるのか、何を託すべきなのか、若者の心が離れない地域の在り方を示せるはずです。若者が真に留まりたい、あるいは戻りたい故郷の姿を描き、郷土を想う人財を育てることで、そう遠くない将来、熊本の魅力を語り合い共に地域をつくる仲間が増えることに繋がります。
今後の熊本の魅力は、熊本に来ることでしか体験・経験できないそのような「こと」の創出が求められています。なぜなら、その地域の物を買おうと思えばインターネットを使うことにより簡単に購入することができる世の中になったからです。このように欲しい物をより便利で簡単に入手することが全国的にできるようになり、いつでも必要な物が手に入るようになった結果、商品の機能自体の価値よりも、商品購入だけでは得ることができない、「こと」に対する消費意欲が高まっているのです。
これからのまちを創造する若者と共に郷土熊本が持つ新たな魅力を発見し、国内外の人にどのような「こと」が求められているのか、小さな「こと」でも熊本の魅力を発信していきます。
スポーツを通したまちづくり
昨年、4年に1度のスポーツの祭典、夏季オリンピック・パラリンピックがパリの地で開催されました。オリンピック憲章の基に様々な競技が行われ、世界中の人を魅了しました。選手一人ひとりが勝利を目指して努力をしてきた成果によって、メダルを勝ち取る姿や真剣に取り組む姿勢に人々は感動します。また、選手にはそれぞれのストーリーがあり、勝ち負けだけではない困難を乗り越える姿や選手間の絆など多くの物語が生み出され、感動が皆の心に残ります。それは、スポーツを通して国境や年齢、人種を越えた他者を理解する心を育み、スポーツの持つ最高の力となるのです。
熊本青年会議所は、スポーツを通したまちづくりを推進していく中で、各スポーツチームの横連携を強めようと「くまもとスポーツユナイテッド(以下 KSU)」という組織を2023年に立ち上げました。昨年度は、熊本県知事や有識者たちをお呼びし、熊本のスポーツを通したまちづくりを進める上で重要な新たなスポーツ施設の建設に向けての議論の場となるフォーラムを開催し、それぞれの立場がどのように考えているのかを確認しました。その際に知事は「県民一人ひとりがどのように望むのかそれ次第である」とお答えになられました。KSUを立ち上げた熊本青年会議所としては、議論を県民運動へと昇華させる機会を創出し、情熱をもってスポーツを通したまちづくりの運動を展開していかなければなりません。
スポーツの力を積極的に活用して、少子高齢化をはじめとした地域の様々な課題を解決し、住民の健康促進はもちろん、地域の活性化(地方創生)・まちづくりの実現に寄与していきます。
政治参画意識の醸成
2024年熊本県知事選挙でも若者の投票率を高めるための啓発活動が活発に行われましたが、若者の投票率は依然として低い状況です。投票意向は高いものの、実際の行動になかなか繋がっていない原因として、以下の二つが考えられます。一つは、政治家の属性が偏っていることから、政治が身近に感じられないということです。政治の場に様々な年代や性別の人が参加する環境になることが望まれています。もう一つは、若者が政治を自分ごとに感じられる情報が少ないということです。常に情報過多な環境に生きている若者は、興味のある情報ですら最初の情報接触の姿勢は受動的です。また、若者が政治に関心を持つことができないのは、社会全体の風潮として政治に対してマイナスのイメージが強いことが大きく起因しており、このことに向き合っていかない限り、若者はおろか国民の政治離れを食い止めることはできません。
私は、若者が政治に関心がない、若者が選挙に行かないことは、まちづくりに対しての実体験の不足からなるものだと考えています。自分たちの働きかけでまちが変化するのを目の当たりにするうちに他人事だったまちづくりを自分事として捉えるようになり当事者意識が芽生えるのです。このような主権者教育やシティズンシップ教育を推進することで政治参画意識の醸成に繋げていきます。
熊本青年会議所では政策本位の投票とマニフェストサイクルの定着を目指し、熊本市⾧ローカルマニフェスト検証会を2005年から毎年継続してきました。本年も、任期3年目の熊本市⾧ローカルマニフェスト検証会を厳格な調査、裏付けを持って開催します。マニフェストが選挙の際の判断材料になることは勿論、選挙後も市民団体がマニフェストの進捗を検証していくことは市政に対して緊張感を与えることにもなります。また、検証を続けていくことで政策の具体的な数値目標、達成期限、財源が実現可能なマニフェストになっているか、選挙によって政治に参画する我々市民も、政策から地域の未来の姿を描く力を養っていかなければなりません。このローカルマニフェスト検証会を⾧年行なってきた熊本青年会議所から政策本位の投票の必要性を市民に啓蒙します。さらに、2024年の東京都知事選挙・衆議院解散総選挙では、若者の政治参画意識が向上する形となり、SNSを使った選挙の在り方や討論会が候補者の政策や思想を知る大きなツールとなり、政治への関心も高まりました。このタイミングでより一層若者の政治参画意識の醸成に繋がる運動を展開していきます。
組織強化
青年会議所の特徴の一つとして、単年度制で毎年役職や担いが変わるという点が挙げられます。継続事業というものも基本的になく、同じような事業であっても、検証を踏まえて毎年少しずつ改善を加えていくのが青年会議所の基本的な仕組みです。しかし、青年会議所が設立されて以来、唯一途絶えることなく継続している事業があります。それが会員の拡大です。それは青年会議所のみならず、企業や他の組織においても必要なことです。そして、この青年会議所という組織は年齢制限があり、全ての会員が40歳で卒業します。青年会議所にとっては毎年経験豊富な会員を失う欠点がありますが、その欠点に勝る最大の利点が、組織が1年単位で新陳代謝することです。
新たな会員を迎えることで、社会課題解決能力を組織として高めていくことが可能となり、同時に青年が社会により良い変化をもたらすための発展と成⾧の機会を提供することに直結します。そして、量だけの目標では共感は生まれません。古今東西すべからく、魅力のある場には人が集まり、人が集まらない場には集まらない理由があります。魅力ある組織とは共通の目的、目標を有した人の集合体であり在籍する会員が組織理念を追求し現実化する組織です。さらに、組織理念が会員の行動として外部へ伝播し、共感を生み出す先に組織の成⾧、発展があります。
また、候補者にとって入会は目的ではありません。会員拡大する側にとっては入会申込書に印鑑をもらったところで、ひと段落します。しかし、候補者にとっては、この入会した時からが始まりであり、成⾧の機会や成果が得られるという期待に満ちた一番モチベーションの高い状態となります。その状態で活動を続けていけるように、時代にあわせた育成プログラムを計画し、チームで一人ひとりの候補者を正式入会へと導いていける仕組みを構築していきます。
マインドシフトへ向けた学び
世界経済フォーラムは、毎年各国のジェンダーギャップ指数を計算して公表しています。ジェンダーギャップ指数は「経済」「政治」「教育」「健康」の4つの分野データから算出されており、日本は先進国最下位となっています。日本において女性活躍が進みにくい大きな原因として、「家庭や学校における男女別の役割の固定概念の植え付け」「女性総合職の候補者不足」「入社後のキャリアでの壁」の3つが挙げられています。そして「入社後のキャリアでの壁」については、「仕事と家庭のバランスを取ることが困難」「労働市場が流動性に乏しく、キャリアを中断すると復帰が困難」という要素が、大きな原因になっています。さらに、女性の上級管理職に採用される割合は、主要国では36%で、日本では、12%台と世界と比較しても低い水準のままです。そして、熊本青年会議所においても女性会員は10%であり、理事役員となると5%を下回ります。今後の女性社会進出を促しジェンダーギャップを下げる運動を推進することにより熊本の大きな社会課題である労働人口の減少に寄与できると考えています。
世界では生成AIが現れたことにより、私たちの働き方を大きく変えつつあり、デスクワーク中心の職務に就いている人の4人に3人が現在、生成AIを業務に活用しています。この新しいテクノロジーには新しいスキルが必要です。リンクトイン(世界最大手雇用サイト)は、2030年までに世界の仕事に必要なスキルセットが68%も変化すると予測しています。
その多くは、チームリーダーシップ、戦略的リーダーシップ、コラボレーションなど、メンバーと共に仕事を進める際に役立つ、対人的なソフトスキルになることが予想されています。リンクトインのプロファイルに掲載されるスキルのうち、ソフトスキルについては女性が男性よりも28%多いことが分かっています。さらに、2016年以降AI人材における女性の割合が大幅に増加しており、とりわけAIエンジニアリングに従事する女性が増えています。つまり、生成AIの登場は、ジェンダー・ギャップを解消する好機なのです。
熊本青年会議所においても、女性の会員に対する意識や考え方について意見を交わし、志高き青年が活動しやすい環境についての議論を進めていきます。
働き方改革5.0
近年の技術革新等の変化に直面し、ライフスタイルが多様化する中で就労面からの働き手から選ばれる企業となるために、心身ともに健康でいられて社会的にも満足できるウェルビーイングを重視した職場環境や制度づくりが求められています。そのためには、労働者一人ひとりが、自ら望む生き方に沿った豊かで健康的な職業人生を安心して送れる社会を築くことが重要です。働く意欲はありつつも、様々な事情により働けない人々について、こうした事情を一つ一つ取りのぞいていくことにより、働くことを通じた活動の機会を提供します。それは、単に収入を得る手段としてではなく、社会参加の一つとして、人々の生活を豊かにするものと考えられます。熊本市においても多様性や包摂性のある社会の実現を目指しており、青年経済人が集まる熊本青年会議所としても組織や会社の発展に繋げていき、時代に即した思考や価値観を身に着ける必要があります。
また、人口減少が進む熊本においては、就業率の向上を図り、社会としての活力を維持する観点からもウェルビーイングの向上は重要です。その為には女性の活躍推進に向け、男性の家事・育児・介護等への参画推進や育児・介護と仕事を両立しやすい職場環境の設備や⾧寿化に対応し、年齢にかかわりなく希望に応じて働き続けることができるよう、高齢者の雇用・就業環境の設備の改善を行っていく必要があります。
就業面からのウェルビーイングの向上と生産性向上の好循環により、選択可能な働き方が増えることで就労機会が拡大し多様な人々の活躍に寄与していきます。
出向について
青年会議所には、出向というシステムがあり、LOMに所属しながら、熊本ブロック・九州地区・日本・世界へと出向する機会があり、その機会は学びや成⾧に繋がり、人生を豊かにしていきます。「個の成⾧」「LOMの成⾧」「まちへの貢献」など一見LOMでもできることだと感じる部分ですが、LOMと出向の両方を同時に経験することは2倍以上の効果があると感じています。私自身、日本青年会議所に出向する機会を多くいただき、出向する度に日本の抱える課題解決に向けた、政策や事業を考えて運動を展開してきました。日本というマクロの視点から物事をみて、熊本市というミクロの視点へと繋げることにより、今までとは違った気付きや課題を抽出できるようになりました。また、日本青年会議所は、2年から3年先の世の中のトレンドとなるような先進性のある課題解決へ向けた取り組みをおこなっています。それらの情報を取りにいく事で、熊本のまちづくりに繋がる運動への展開が可能となるのです。
外から見ないと気がつかない気付き、例えば、他の青年会議所と比較したときの熊本青年会議所の優れている部分や改善点、熊本のまちの特徴、そして出向組織特有の多様な発想や活動など、広く行動すればするほどその機会はあなたの視野を広げ柔軟な発想を生み出してくれます。新たな友達を作るのもよし、一緒にビジネスをするのもよし、出向する楽しさを自身で見つけていくことで、新たな価値観を見出してほしいと思います。その出向者が出向できる環境や成⾧できる環境を作っていけるように最大限の支援をしていきます。
熊本青年会議所の災害支援
2016年4月14日21時26分に熊本地震が発災しました。それから、すぐに会員の安否確認から緊急でミーティングをし、翌日には炊き出しをおこないました。それから約2ヵ月間、毎日、ヒアリング調査や全国各所から届く物資を集荷し搬送する先輩方に、当時は尊敬の念しかありませんでした。私は、その翌年から災害が起こる度に被災地へ入りできる限りの支援活動を続けてきました。誰かのために何かしたいという気持ちは、青年会議所のおかげでより一層強くなりました。当時、先輩たちの姿に引っ張られてお手伝いをすることしかできませんでしたが、災害支援活動をしてきた今なら様々なネットワークを使いより良い支援ができます。これからも日本は災害大国であるため、いつどのようなことが起こるかわかりませんが、起こった際にどのように動くのかを事前に組織として考えていくことで日本全国にある社会福祉協議会やJVOADといったネットワークを使った支援をおこなえると考えています。
これまでの熊本青年会議所の創立の歴史や伝統を継承された我々だからこそできる活動を通じて国土強靭化に寄与していきます。
訪れる危機に向けたBCP
BCPとは、いつ発生するか分からない緊急事態に対し、企業が平常時から備えておくべき重要な計画です。特に近年は、自然災害の発生が増えているため、有事の際でもすみやかに復旧・継続できる体制を築いておく事が求められます。また、災害だけではなく、ウクライナとロシアとの戦争やイスラエルと中東諸国の紛争といった各地で起こっている紛争についても目を向けることが必要です。
日本人としたら対岸の火事という認識かもしれませんが日本という国は、輸入に頼って生活しています。そして、日本の地政学的リスクを見ていく上で重要なのが、「シーレーン」であり、有事の際でも絶対に確保しておかなければならない海上交通路のことを言います。このシーレーンを通って、海外から原油・ガス・鉄鉱石・石炭・穀物など、あらゆるものが海を渡ってやってきており、日本で消費される殆どのエネルギー資源がシーレーンを通って輸入されているのです。例えば、中東から原油や天然ガスを運ぶ、⾧さおよそ1万2000キロメートルのシーレーンを通って、日本で1年間に消費される原油の9割以上が運ばれています。もし通れなくなると、日本経済に大きな影響を与える恐れがあります。
また熊本は、TSMC(台湾企業)の進出によって、台湾有事に対して関心を高めていく必要があります。私たち青年経済人は、今後起こりうる、様々なリスクを考えて熊本青年会議所としてのBCPや企業としてのBCPを検討していく必要があります。組織や企業がおかれているリスクを顕在化することにより、変化に耐えうる組織や変化をチャンスにできる企業に繋げていきます。
規範ある組織への挑戦
JC運動を進めていくにあたり、LOMの指針との整合性、多角的な議論、コンプライアンスの徹底が重要です。私たちは単年度制の団体であるからこそ、この点を基軸に定期的に意思統一を図る機会を作り、その時々にあった情報共有と意思の再確認を行うことが重要です。そしてその最たるものは議案を通して行われます。LOMの指針に沿った議案が作成され、それを基に議論が行われ、コンプライアンスの徹底により事業に信頼が寄せられます。しかし、近年は議案に対する苦手意識が強くなっているように感じています。その原因はシステムに対する理解不足と経験不足によるものです。これらを解決できれば、より良い議論が交わされる会議となり、より意思統一がされ、事業への展開が可能となります。
時代の流れの中で組織のガバナンスの形は変化を遂げるものの、私たち青年会議所の会員の所謂プロトコルたる「決め事」は、ただそこに存在するだけでは何らの意味も持ちません。それぞれの会員がプロトコルそのものを行動規範の中心に据え、明文化された中身の一つひとつを理解し、行動や言動で体現することで初めてその価値が認められます。この決め事の在り方が適正であるか、また新たな要素を付加できないかを積極的に議論することでルール自体が磨かれ、ルールを運用する組織そのものも磨かれます。また、会費収入が運営の主たる原資である熊本青年会議所においては、健全で強固な財務基盤の確立には厳格な審査が必須であり、各支出に合理性が認められるか、運動の効果を最大限に高めるものであるか、画一的な基準に当てはめて検討することが重要です。何より、会員の成⾧、入会者の増加、組織の信用向上といった支出に見合うだけのリターンがどのような形で発生し、組織を超えて市民、地域にどのような形で好循環をもたらすのか、公正で冷静な判断を要します。
それら規範を基に、より効率的に実現していくための実務上の改革が次の世代の組織のあるべき姿に直結するはずです。規範とは、「判断・評価・行為などの、拠るべき規則・規準」です。つまりは、互いに規範こそが道徳的な価値観であり「ものさし」だと言えます。正しいものさしを持ち、規律を重んじることで、定めたルールが遵守され組織の成⾧へと繋がり、JC運動がより推進されるのです。
本年度は、1年のスタート時に全ての事業の方向性を共有することを初めの規範とし、1つ1つの事業を邁進していきます。
今後の担い手にむけて
青年会議所には、事務局という様々な業務をおこなう役職があります。様々な機会を自らつかみにいき成⾧に繋げる青年会議所ならではの役職であり、組織全体が効率的に機能するよう洞察力と想像力をもってアシストするセクレタリーの役割を担っています。単に秘書としてのスケジュールの管理や会議の運営だけが求められているのではなく、正副と同行し様々な活動に直に触れ、将来自分が同じ立場になった場合のシミュレーションを行うことも求められております。本年度は、属人的になりやすく効率化することが難しい業務を平準化し、グループセクレタリーの意識をもって活動していきます。
中⾧期戦略会議が発足して4年目を迎え、熊本青年会議所の今後を担う若い会員が増えています。これからの時代は「SuperVUCA」の時代と呼ばれており、不安定で不確実で複雑で曖昧な状況が続き、常に変化していくことを前提に考え、これまで以上に1人1人が自律して行動していくことが必要とされます。若手の会員だけではなく、組織全体として、必要とされるスキルや考え方を学ぶ機会を創出し個々の成⾧に繋げていきます。
Discipline(規律)
マネジメントでいう「規律」とは組織の価値観に従うということです。つまり、「規律を守る」ということは、組織が大切にしていて、何よりも優先していることに従って行動するということです。その規律は、現状と達成したい目標との架け橋となります。
まず、会員には青年会議所の活動をしている理由を問いかけます。熊本の明るい豊かな社会の実現を目指すのであれば、その為にどのような行動や運動を起こす必要があるのか、そこに結び付く具体的な目標を明確にします。正しい目標設定ができれば、プロセスが見えるので、担いを預かった組織が責任をもって推進していくことができます。その結果、組織の目標達成・自己の成⾧へと繋がっていくのです。
規律を維持するには、「マインドセット」「スキルセット」「ストラクチャー」の3つが重要です。まず、考え方や目的に対する方向性にズレが生じているのであれば、お互いが現状の課題に対して真剣に向き合い、コミュニケーションを取り共有する必要があります。そして個として必要な能力と組織として必要な能力に対して評価し、改善に向けたアドバイスをすることで、個・組織としての能力の向上を図る必要があります。さらに、担いや目標に向けてのプロセスを、組織の全員が理解できている構造がつくれているかどうかが重要となります。
これらが確立していれば確実に会員の成⾧が実現し、組織の規律が生まれます。リーダーが規律の欠如を嘆く時、実はリーダー自身が3つの要素を正しく設定できていないことが多いのです。意識を変革し、地域に好循環を生む団体の一人ひとりが自己成⾧をしていける組織を目指していきます。
家族・会社・JC活動
最近、青年会議所の活動により会社の業績が良くなった、活動に前のめりになりすぎてライフバランスを崩し業績が悪化した、家族の理解が得られている、得られていないなどの両極端の話を聞くことがあります。社会の最小単位は家族であり、家族や会社が上手くいっていなくては、熊本の明るい豊かな社会の実現は成り立ちません。熊本青年会議所のある先輩は、「家族・会社は同じくらい大切なもので、それにいかにJC 活動を近づけることが大切」と言われておりました。まさにその通りで、何かを犠牲にするJC活動ではなく、JC活動を通して家族・会社・地域を良くしていかなければなりません。そのような活動へ向けて、ただ出事を減らす・会議の回数を減らすといった効率だけを求めるだけではなく、効果の最大化を目指す中で生産性の向上を実現していく必要があります。
青年会議所運動の本質を変えることなく、本質にそぐわない部分は不断の決意で変えていき、すべての会員が「家族・会社」を第一に考えた組織へと変革して、明るい豊かな社会の実現を目指していきます。
最後に
「JCは、まちを想う青年を大きく成⾧させ、大人に永遠に郷土愛の心を抱かせる。JCから学んだ事は、利他の精神で世の中の為に生きていく事だ。だからJCは、素晴らしい。」
私がラグビーから学んだことの多くが、JCにも共通しており正にこのように思います。
そして、熊本青年会議所に様々な成⾧の機会をいただき感謝しています。
感謝とは、他人から受けた恩恵や善行に対して、心からありがとうと思う気持ちのことを指し、日々の生活の中で人々が互いに助け合い、思いやりを持って接することの大切さを教えてくれます。
感謝の心を持つことで、私たちは自分自身と他人とのつながりを感じ、人生をより豊かにすることができます。
豊かな心で品位・情熱・結束・規律・尊重をもって、熊本青年会議所の活動を通し、家族・会社・地域を豊かにしていきたい。
時代の変化を恐れず、青年らしい理想を掲げて挑戦していこう!
スローガン
感恩戴徳(かんおんたいとく)
基本理念
青年らしい理想を掲げて
感謝の心をもって共に結束し
夢と魅力溢れる豊かな熊本へ
基本方針
感謝の心を持ち歴史を継承し夢溢れる未来を創造
組織の価値を高める発信と多様性を育む国際都市への挑戦
青年らしい情熱と発想による魅力ある新しい熊本の実現
新たな仲間と共に成⾧し共感を生む組織の拡大
規範と規律を遵守する組織運営

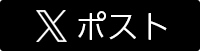

 一般社団法人 熊本青年会議所
一般社団法人 熊本青年会議所